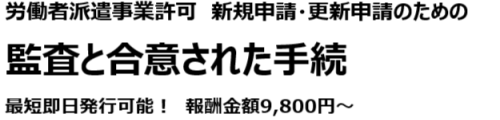なぜ低資本金スタート? 労働者派遣事業許可申請と消費税免税の知られざる関係
人材派遣ビジネスへの参入を志す起業家の皆様、あなたの心には今、どのような青写真が描かれているでしょうか?
「社会に貢献したい」「人の働くを支えたい」「新たな雇用を創出したい」――その熱い想いを胸に、あなたは今、事業者としての第一歩を踏み出そうとしていることでしょう。
しかし、その輝かしい夢のすぐ隣には、避けては通れない「許可申請」という名の関門が立ちはだかります。中でも特に多くの起業家が頭を悩ませるのが、「財産的基礎の要件」です。
ご存知の通り、労働者派遣事業の許可を得るためには、原則として「自己名義の現金・預貯金が1,500万円」「基準資産額が2,000万円以上」という厳しい要件をクリアする必要があります。
この要件を満たすために、多くのコンサルタントや専門家は、新規設立の会社であれば「設立時の資本金を2,050万円や2,100万円に設定すること」を推奨します。
「王道」とされる高額資本金設立のメリット
なぜ、資本金2,050万円や2,100万円での会社設立が「王道」とされているのでしょうか?
その理由は、許可申請のプロセスを劇的に簡素化し、時間と手間を大幅に削減できるという明確なメリットがあるからです。
- 監査証明が不要になる: 労働者派遣事業の許可申請において、財産的基礎の要件を満たしていることを証明する方法の一つに「公認会計士または監査法人の監査証明」があります。しかし、これは時間も費用もかかるプロセスであり、新規設立法人にとっては大きなハードルとなります。 設立時の資本金が2,050万円以上であれば、原則としてこの監査証明が不要となります。会社設立時の資本金が、そのまま財産的基礎の要件を満たしていると認められるためです。
- 決算期を待たずに申請できる: 監査証明を得るためには、通常、会社の月次決算を一度終える必要があります。つまり、会社を設立してから月次決算の作業を終え、監査を受け、それからようやく許可申請に踏み切る、という時間的な制約が生じます。 しかし、設立時の資本金が高額であれば、一度も月次決算を経ることなく、設立後すぐにでも許可申請のプロセスにコマを進めることができます。これは、一日も早く事業を開始したいと願う起業家にとって、計り知れないメリットです。市場の機会を逃さず、競合に先んじて事業を立ち上げることが可能になるのです。
このように、高額な資本金での会社設立は、許可申請のプロセスにおいては、まさに「最短ルート」「最少の手間」を実現する、理にかなった正攻法であると言えるでしょう。
それなのに、なぜ? 多くの会社が「遠回り」を選ぶ「謎」
しかし、ここで一つの疑問が浮上します。
これほど明確なメリットがあるにもかかわらず、私たちの目には、あえて資本金100万円や200万円といった低資本金で会社を設立し、その後、2,000万円超に増資して監査証明を取得し、許可申請にコマを進める会社様が、驚くほどたくさんいらっしゃるのが現状です。
「なぜだろう?」
そう思わずにはいられません。わざわざ増資の手間と登記費用をかけ、さらに監査証明というコストと時間を要するプロセスを経る。
一見すると、これは非効率で、無駄な「遠回り」にしか見えません。
しかし、賢明な起業家や経営者が、何の考えもなく、わざわざ遠回りを選ぶはずがありません。彼らは、一体何を重視し、どのような「メリット」を見出しているのでしょうか?
この「謎」を解き明かす鍵は、実は、「労働者派遣事業許可」という法的な要件とは、全く別の領域にある「税務」の視点に隠されています。
謎解き:賢明な経営判断の裏にある「消費税」の壁
多くの起業家が低資本金での設立を選ぶ最大の理由。それは、ずばり「消費税法の新設法人に関する特例(消費税免税事業者制度)」にあります。
消費税は、企業活動において売上の一部として顧客から預かり、国に納める税金です。しかし、全ての事業者が消費税を納める義務があるわけではありません。一定の要件を満たすことで、消費税の納税が免除される「免税事業者」となることができます。
この免税事業者制度には、新しく会社を設立する際に適用される、重要なルールがあります。
【消費税の基本ルール】 消費税の納税義務がある「課税事業者」になるかどうかの判定は、原則として「基準期間」と呼ばれる期間の課税売上が1,000万円を超えるかどうかで行われます。基準期間とは、簡単に言ってしまえば、個人事業主なら前々年、法人なら前々事業年度を指します。
【新設法人に適用される特例】 しかし、新しく設立された法人には、この基準期間が存在しないため、特別なルールが適用されます。
- 資本金1,000万円以上の法人: 設立時の資本金が1,000万円以上の法人は、原則として設立初年度(第1期)から自動的に課税事業者となります。 これは、設立時の資本金が大きい企業は、ある程度の事業規模が見込まれるため、設立当初から消費税の納税義務を課すという考え方に基づいています。
- 資本金1,000万円未満の法人: 一方、設立時の資本金が1,000万円未満の法人は、原則として設立初年度(第1期)と、その翌事業年度(第2期)の2年間は「免税事業者」となることができます。 ただし、特定期間(事業年度開始の日以後6ヶ月間)の課税売上が1,000万円超、または給与等支払額が1,000万円超の場合は、その期間の終了後から課税事業者となるなど例外規定もあります。
免税事業者となることの「衝撃的な」メリット
この「設立後2年間、免税事業者となれる」という点は、特に事業の立ち上げ期にある企業にとって、計り知れないメリットをもたらします。
- キャッシュフローの劇的な改善: 消費税は、売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかる消費税を差し引いて納める仕組みです。課税事業者であれば、売上が上がれば上がるほど、その一部を消費税として預かり、いずれ国に納めなければなりません。 しかし、免税事業者であれば、顧客から預かった消費税を国に納める必要がありません。これは、預かった消費税分が企業の手元に残り、運転資金として活用できることを意味します。 事業の立ち上げ期は、人件費など、何かと出費がかさむものです。この時期に消費税の納税負担がないことは、資金繰りに大きな余裕をもたらし、事業を軌道に乗せるための重要な下支えとなります。特に、労働者派遣業は売上が先行しやすい業態であり、初期の消費税負担は、キャッシュフローにとって非常に大きなインパクトを持つことになります。
- 価格競争力の維持: 免税事業者は消費税を納める必要がないため、課税事業者と比較して、理論上は同じ売上でも利益率が高くなります。これにより、価格設定の自由度が増し、競合他社に対して価格競争力を持つことが可能になるケースもあります(もちろん、インボイス制度の影響は考慮が必要ですが)。
インボイス制度導入後の「2割特例」が、さらに背中を押す
2023年10月に導入された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、消費税の納税義務者にとって大きな転換点となりました。仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者(課税事業者)からの適格請求書が必要となるため、免税事業者の中には、取引先の要望などから、あえて課税事業者を選択するケースが増えました。
しかし、ここで、低資本金設立のメリットがさらに活きてくる可能性があります。
【2割特例とは(令和7年7月現在)】 インボイス制度への対応で新たに課税事業者になった事業者(主に、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者)が選択できる、特別な消費税の申告方法です。 この特例を適用すると、預かった消費税額の80%を「みなし仕入れ率」として差し引くことができ、預かった消費税の20%だけを納付すればよい、という非常に有利な制度です。 例えば、課税売上が1,100万円(うち消費税100万円)で、仕入れ等の消費税が20万円だった場合、原則的な方法だと100万円 - 20万円 = 80万円の納税ですが、2割特例だと100万円 × 20% = 20万円の納税で済むことになります。
この「2割特例」は、2026年9月30日までの課税期間に適用が可能です(令和7年7月現在の情報)。
つまり、低資本金で会社を設立し、最初の1年間を免税事業者として運営し、もしインボイス発行のため課税事業者を選択する必要が生じた場合でも、この2割特例を適用することで、消費税の納税負担を低く抑えることができるのです。これは、設立当初の資金繰りにとって、非常に大きな安心材料となります。
「遠回り」は、実は「最良の戦略」だった
このように、低資本金で会社を設立し、後から増資と監査証明を経て労働者派遣事業許可を申請する「遠回り」に見える方法は、実は、「事業立ち上げ期の初期負担(特に消費税)を極力抑え、キャッシュフローを最大限に確保する」という、極めて戦略的かつ賢明な経営判断に基づいているのです。
許可取得までの時間や手間が増えるというデメリットはありますが、それと引き換えに、事業を健全に成長させるための「資金」という、最も重要なリソースを温存できるという、計り知れないメリットを享受できます。
特に、労働者派遣事業は、売上や人件費が大きくなるにつれて消費税額も大きくなる傾向があるため、初期の消費税免除や軽減措置は、事業の安定と成長に直結する重要な要素となります。
あなたにとっての「最善の道」を選ぶために
結局のところ、会社設立時の資本金をどうするかは、それぞれの起業家の資金状況、事業計画、そして何よりも「何を最も優先するか」という経営判断によって異なります。
とにかく一日も早く許可を取り、事業をスタートさせたい! という場合は、高額資本金での設立が理にかなっています。
お問い合わせ
預金不足の解決策、純資産不足の解決策、合意された手続、監査のお問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 労働者派遣事業許可に必要な監査や合意された手続に精通し、数多くの企業をサポートしてきました。日々の業務では「クライアントファースト」を何よりも大切にし、丁寧で誠実な対応を心がけています。監査や手続を受けなくても財産的基礎の要件をクリアできる場合には、そちらを優先してご提案するなど、常にお客様の利益を第一に考える良心的な姿勢が信条です。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
最新の投稿
 お知らせ2025年7月28日基準資産額を増やすための「税効果会計」の活用法
お知らせ2025年7月28日基準資産額を増やすための「税効果会計」の活用法 お知らせ2025年7月25日なぜ低資本金スタート? 労働者派遣事業許可申請と消費税免税の知られざる関係
お知らせ2025年7月25日なぜ低資本金スタート? 労働者派遣事業許可申請と消費税免税の知られざる関係 お知らせ2025年7月7日労働者派遣事業許可申請:財産的基礎の要件クリアへの道筋 – 3つの選択肢と最適解
お知らせ2025年7月7日労働者派遣事業許可申請:財産的基礎の要件クリアへの道筋 – 3つの選択肢と最適解 お知らせ2025年7月5日労働者派遣事業許可申請における「監査」と「合意された手続」の違いを徹底解説
お知らせ2025年7月5日労働者派遣事業許可申請における「監査」と「合意された手続」の違いを徹底解説